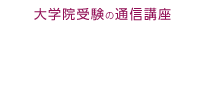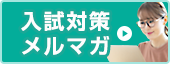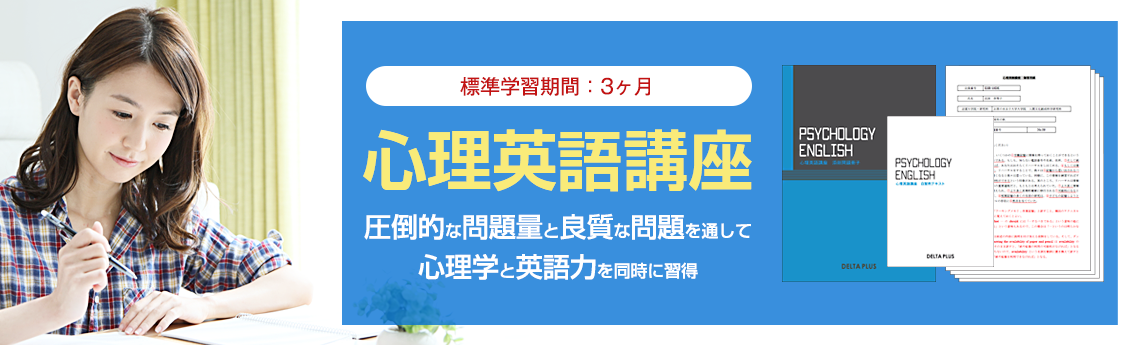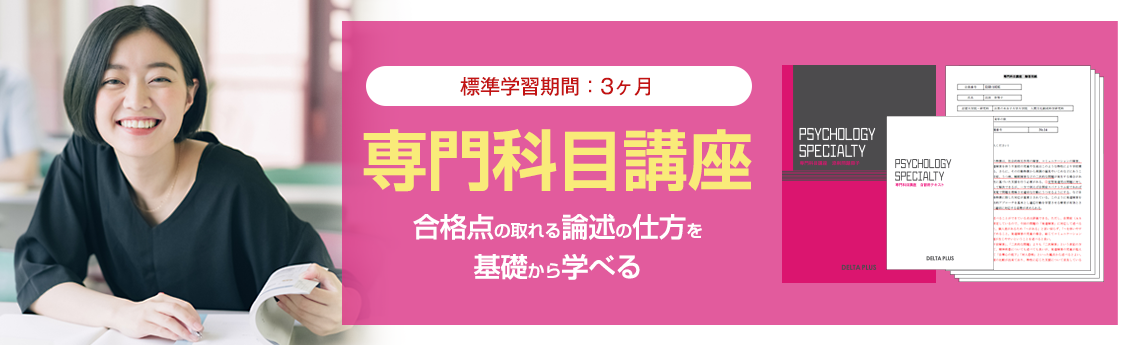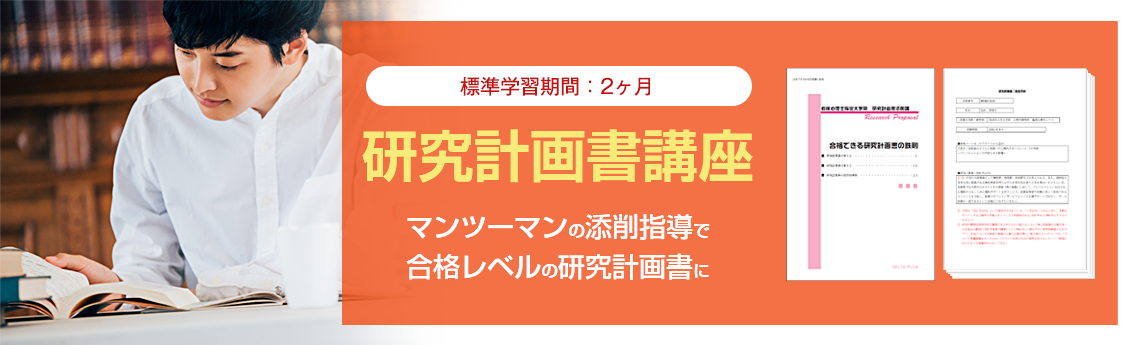合格実績
上智大学大学院 総合人間科学研究科 合格
自分のリソースの配分を見極め、優先順位づけを行うこと
神奈川県 もも さん
論述だけは誰かに見てもらいたいというニーズにぴったり
論述問題で問われそうなポイントをできるだけたくさん知っておきたくて、「専門科目講座」を受講しました。私は心理学科の大学生だったので通学するほどではない、英語や研究計画書のサポートも不要、でも論述だけは誰かに見てもらいたい。そんなニーズにぴったりだったのが『心理系大学院 入試対策講座』でした。
基礎心理学科目・応用心理学科目に共通していた勉強法は、科目ごとの用語ノートのまとめです。勉強すればするだけ、毎日知らない用語と出会ってしまうので、適切な箇所に追記・更新できるよう、アナログではなくデジタルノートにしました。論述対策はこの用語まとめが一段落した後に取りかかりました。論述対策は過去問分析がカギだと思います。基礎系科目ではとにかく用語拾いに徹し、論述対策はほぼ臨床系を中心にしました。基礎系の中でも社会心理学だけは好きだったので、対策本を使ってしっかり準備しましたが、生理心理学や認知心理学は正直捨てました。
自分のリソースの配分を見極め、優先順位づけを行うこと
講座の活用法としては、とにかくテキストを使い込むことです。講座のテキストは本当に優秀です。「添削問題冊子」も「自習用テキスト」も、模範解答だけでなく論述に必要な背景知識まで、適度に深く、かつ簡潔にまとめられています。ネットや教科書を読んでもいまいちしっくりこなかった単語の定義がすっと腑に落ちることもありました。論述の構成と覚えやすい表現に出会える点がこのテキストの魅力だと思います。
添削は確か6回分使えたと思いますが、私は2、3回しか利用していません。というのも、私は内部生(特別措置なし。匿名試験で、教授は誰の解答用紙かわからないまま採点する仕組みです)で各教授のこだわりを知っている自分としては、答案を返していただいても「あの教授はこんなところを気にしないだろうな…」とわかっていたので、添削指導はあまり利用しないことにして、この素敵なテキストを最大限に利用できることに講座の価値を置くことにしました。時間が限られていたため、テキストの問題に全部取り組むより、志望校の教授が好きそうな分野を想定して「オリジナル論述問題」を作って解く練習をしていました。自分のリソース(教材・時間・お金・人脈)をどう配分するべきかを見極め、しっかりと優先順位づけを行うことが重要だと思います。市販では手に入らないテキストで、知識の補完も論述対策もできるのは非常に心強かったです。周囲との差別化にもつながり、自信を持って本番に臨めました。
膨大な量の知識を吸収できたので、大学院受験の経験は大きなものとなった
公認心理師の資格取得に向けて大学院で学び、その後はスクールカウンセラーとして働きたいと考えています。「いじめ加害者支援」普及が私の高校生の頃からの目標で、その夢を生涯かけて実現していくためのほんの小さなプロセスに過ぎないのですが、この大学院受験の経験は私にとって本当に大きなものとなりました。私の人生にとって大きいと言える理由は、受験勉強が難しすぎて受験期がつらすぎたから、というのもそうですが、何よりこの期間で増えた心理学の知識の量が膨大だからです。私はまじめな学生ではなかったので、大学の授業中もずっとスマホを触るばかりでまともに授業を聞いたことがありませんでした。ですから、この受験勉強は基礎のキソから始めました。普通に心理学の大学生をやっていれば頭に入っているのかもしれない基本のキすら私にとってははじめましてですから、インプットしなければならない知識が多すぎました。受験が終わってオリジナルノートのルーズリーフのページを床に並べてみたら、我が家のリビングの床を埋め尽くす面積となりました。その量を頭の中に入れて入試本番は戦わなくてはならないので、かなり大変でした。しかしこの大学4年生という時期に一度教科書的な知識をしっかりと吸収したことは、この先の大学院での勉強、そして公認心理師資格の取得に必ず生きてくると思います。もちろん、その後に続くであろう心理職としての働きにもです。
「この分野の話なら私に任せて!」と言えるラインを目指す
「論述に自信がない」、「不安すぎて心が折れそう」という、そんなあなたにこそおすすめです。知識の量も質も、確実にレベルアップします。もう受験勉強を始めている方は、勉強の不安で心が折れそうになっているかもしれません。他の体験談を見ていると、なかなか冷静な先輩方が多くて、余計不安になったりしませんか? 私はそうでした。「激ヤバどん底だったけど乗り越えた」みたいなエピソードに出会いたいのに、まず体談が少ない上、みんな結構冷静。「こんなに不安なのは私だけなのか?」と、本当に怖かったです。でも、大丈夫。不安だらけだった私も第一志望(単願)に合格しました。どのテーマでも、「この分野の話なら私に任せて、私に解説させて!」と言えるラインを目指して、表面的な暗記にとどまらず、解説力まで身につくように努力・工夫すること。それが少しずつできてくると、同期の間で本当に教え合うことができるようになってきて、自信につながりますし、実際本番で自信を持って解答できます。
大学の論述試験は、高校生までの定期テストのように答えがあるものじゃないから難しい、とかよく言いますよね。でも心理学はそうではありません。実は「見えない解答の型」があります。そのため、問われ方のポイントをつかんで、応用力を鍛えていけば、初見の問題にも対応できます(「見えない解答の型」とは、例えば精神疾患の治療について問われたら、ついつい心理学的支援のことだけ論じたくなってしまいますが、実は「生物・心理・社会モデル」に沿って答えるように聞かれているなどです)。論述問題の数をこなして「見えない解答の型」を獲得していくことが、「解いたことない問題出たらどうしよう…」の不安低減に効果あり、だと思います。
大学の授業をしっかり聞くと、受験勉強がはるかに楽になる
いつか院試を受ける予定でこの体験談に辿り着いている1・2年生がいたら、あなたは意識が高くて非常に偉いです。尊敬します。私が初めて過去問を見たのは3年生になってからでした。まったく何を言っているのかがわからない問題用紙を見て絶句したことをきっかけに、私は大慌てで受験勉強をスタートしたので、過去問はできる限り早めに見てみることをお勧めします。そして、とにかく大学の授業をしっかり聞くこと。受験勉強がはるかに楽になることでしょう。受験時期、何度「1年前にタイムリープして授業をすべて受け直したい」と悔いたか数え切れません。「私の屍を越えていけ」、「私を反面教師に頑張れ」と思います。どうか授業を大切にしてください。
湯川彰浩から一言